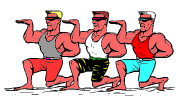 Cyber
Space Clinic・心理学関係の「資格」取得情報
Cyber
Space Clinic・心理学関係の「資格」取得情報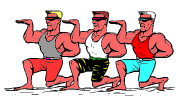 Cyber
Space Clinic・心理学関係の「資格」取得情報
Cyber
Space Clinic・心理学関係の「資格」取得情報
From: "山本 良" <ryo@venus.jstar.ne.jp>
Subject: 「産業カウンセラーの養成講座」受講日記1
今月の10日より「初級産業カウンセラー養成講座」が始まりました。11月まで計17日間の日程です。土曜日か日曜日に講座があり、午前中は講義で午後は面接実習というパターンです。(どちらも3時間30分間)毎週あるわけではないのですが、出欠はかなり厳しく、2日間休むと修了できないようになっています。修了していないと、肝心の試験は受けられないし、労働省の「教育訓練給付金制度」の対象からはずれることになります。
ちなみに、認定試験は筆記試験と実技の試験と二つあります。また教育訓練給付金制度」というのは、労働省で昨年の12月1日から始めた「働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度」です。この制度は一定の条件を満たしてなければ受けることができないのですが、クリアしていれば、支払ったお金の80パーセントに相当する額がもどってきます。もちろん講座を修了しているというのも条件のひとつです。
また、この制度は「産業カウンセラー養成講座」だけに限らず、情報処理技術者資格や簿記検定をめざすなど様々な講座にも適用されています。ただ、資格を取得するためのすべての講座に適用されるというわけではなく、適用される講座は「労働大臣指定教育訓練講座一覧」で指定されています。公共職業安定所(ハローワーク)が窓口になっていますので、詳細を問い合わせしてみるといいと思います。ちなみに、私は雇用保険を5年以上支払っているので、あとはこの講座を修了すればOKなのです。
使わない手はありません!!
少し脱線してしまいましたが、講座の内容については次回に報告致します。
とりあえず、一回目のご報告まで。1999.4.26
それでは、またサイバースペースでお会いしましょう。
ryo@venus.jstar.ne.jp 山本 良
![]() From「うさぎ」さん。
From「うさぎ」さん。
Q.研修は今後も定期的に続くのですか?具体的には、個々の企業で心理相談員としてどのような活動をする(できる)ものなのでしょうか?
![]() From:
「なまず」さん。
From:
「なまず」さん。
A.THPにおける「心理相談員」の研修は今年度は計10回行われる予定です。(東京で5回、大阪で3回、名古屋で1回、福岡で1回)
ただ、だれでも研修を受けられるというわけではなく、ある条件を満たしてないと受けられません。
そもそもTHPというのは、労働省がすすめているもので、事業所(企業など)において事業主が従業員に対して行う健康増進措置のこと。健康診断は法律でやらなければいけないことになっているけど、THPについては「努力事項」で強制力はないため、やらない事業所の方が多いです。大企業がほとんどです。
また、THPにおける「心理相談員」というのは資格ではなく、飽くまで中央労働災害防止協会(中災防)という団体の中でしか、通用しないものです。要するに、そこの会員になっている事業所などが、THPをすすめるにあたって、「心理相談員」が必要になるので、じゃあだれかを研修に行かせようということになるわけです。
それと、THPは飽くまで産業医が中心になっています。産業医が核となって、栄養指導、運動指導、保健指導、メンタルヘルスケアと四つのアプローチをするのですが、それぞれに相談や指導をする専門の人がいます。そのうちのメンタルヘルスケアについては「心理相談員」が受け持つという仕組になっているのです。「心理相談員」はメンタルヘルスケアの部分だけを受け持ち、産業医に報告をする形になります。他の三つについても同じような研修があって、その研修をパスしないと相談や指導はできないことになっています。
ちなみにTHPの「心理相談専門研修」についての問い合わせ先は、中災防 健康確保推進部人材開発課 03-3452-3137 です。
Subject: 「中央労働災害防止協会(略して中災防)」主催の「心理相談専門研修(心理相談員養成研修)」「中災防」研修の報告
ご無沙汰しておりました。お元気でしょうか。CSCの方も無事に立ち上がって、今後の動きが楽しみです。さて、過日にお話ししました「中災防」の研修の件ですが、簡単な報告だけでもと思っていたのですが、伸び伸びになりかなり遅れてすみませんです。ようやく、仕事の方も一段落しましたので、以下に報告致します。
「労働安全衛生法」という法律があり、その70条の2に基づいて労働省が策定した「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」というものがあり、通称 THP(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)と呼ばれているのですが、すべての労働者に身体的な面だけでなく精神的な面からも個人個人で健康に配慮するように目指したものです。具体的にいいますと、産業医を中心として、産業栄養指導担当者や運動指導担当者や産業保健担当者や心理相談担当者等に分かれていて、それぞれから健康にアプローチしていくものです。ただ飽くまで健康に配慮するのは、労働者自分自身だということが基本にあります。そのため、ここでいう「心理相談」というのは精神的に健康な状態に保つよう、労働者に気付かせるという役目をもっているものになります。研修のカリキュラムは以前にお送りしておりましたので、(脚注1)だいたいの内容はおわかりになるかと思います。そもそも行政主導のもののため、THP の法的な位置付けについて東京労基局の人の話から始まって、企業での「心理相談」の実際例として、富士ゼロックスと東芝の担当者の話や産業カウンセラーの話があり、グループ討論や発表、ワークなどもやりました。それらの中で特に印象に残っているのはグループ討論でした。ある企業の中で、部下の行動について問題を感じている上司が相談に来たというケースを想定して(ケースを「事例」という言葉で標準化していました)、その事例性の背後に何かあるとして、その事例についてどういう情報が必要か、その情報はどのようにして集めるか、その方法をつかっていいのか、という「心理相談」の本当に初めの段階のものの討論でした。例えば、その部下の病歴の情報が知りたいとなった場合、その情報を家族から聞く、あるいは会社の人事部から聞くという方法をとると考えた時に、その方法が果たして良いことなのか悪いことなのか、あるいはその方法を使った場合の支障は何があるかということを討論していくものでした。企業という組織の中での問題なので、なかなか一筋縄ではいかないものだと感じた次第です。
以上、研修についての概要と所感を書きましたが、行政のものとなると第三者に理解してもらうには、かなりの説明を要しなければならないところがあり、多少説明不足かなとは思いましたが、あまり説明が多くなると、かえってわかりづらくなることもあり、上記のことで大体のことはわかってもらえると思います。在校生のお役に立てばと思っております。
それでは、またサイバースペースでお会いしましょう。(「なまず」 )e-mail: ryo@venus.jstar.ne.jp
 相談室目次にもどる。
相談室目次にもどる。