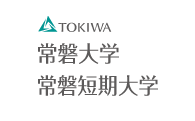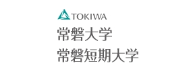教員紹介③ 猪瀬由美子先生
栄養教諭から大学教員へ
「食」を通じて人々の健康を支えたい。その想いを胸に、研究者、栄養教諭、そして大学教員へと転身しました。これまでの経験は、今の自分を形作る上で欠かせないものであると感じています。
栄養教諭としての原点
大学院博士課程修了後、双子の出産を経て中学校の家庭科講師を務めました。特別支援学級の生徒と関わる中で、食生活習慣の改善に取り組みたいという思いが強くなり、地元茨城県公立小中学校の栄養教諭になりました。2024年までの12年間、特に「早寝早起き朝ごはん」の推進に力を入れてきました。子どもたちの食生活の課題を見つけ、解決につなげるためにはどうしたらよいか。これまでの研究経験が食育を推進する上でとても役立ちました。

栄養教諭は、管理栄養士または栄養士の免許を持つ、いわば「給食の先生」です。子どもたちの成長を支える、安心・安全でおいしい給食作り。献立作成はもちろん、栄養バランス、アレルギー対応など、様々なことに気を配りながら、日々子どもたちの健康を見守っています。さらに、給食の時間や授業を通して、食の大切さや正しい食習慣を教えるのも栄養教諭の大切な仕事です。「食」を通して、子どもたちの夢を育む、やりがいのある仕事です。
しかし、栄養教諭はまだ全国のすべての学校に配置されていません。そのため、その存在や役割について、あまり知られていないのが現状です。保健室の先生=養護教諭のように、給食の先生=栄養教諭として、もっと多くの人に知ってもらい、子どもたちの未来を支える栄養教諭を目指す人が増えることを願っています。
しかし、栄養教諭はまだ全国のすべての学校に配置されていません。そのため、その存在や役割について、あまり知られていないのが現状です。保健室の先生=養護教諭のように、給食の先生=栄養教諭として、もっと多くの人に知ってもらい、子どもたちの未来を支える栄養教諭を目指す人が増えることを願っています。
大学教員として新たな挑戦
本学の卒業生には、地域で活躍する栄養教諭や管理栄養士がたくさんいます。私は、地域に根差した実践的な活動を通して、地域で活躍できる栄養教諭・管理栄養士に育てたいという思いから、2024年に本学の教員となりました。
本学は、地域との連携を大切にしています。学生たちは地域に出向き、食育活動など、様々な実践的な活動に取り組んでいます。私も、学生たちと共に地域に貢献し、未来を担う栄養教諭・管理栄養士を育成していきたいと思っています。
大学では、応用栄養学と栄養教諭免許取得のための授業を担当しています。
本学は、地域との連携を大切にしています。学生たちは地域に出向き、食育活動など、様々な実践的な活動に取り組んでいます。私も、学生たちと共に地域に貢献し、未来を担う栄養教諭・管理栄養士を育成していきたいと思っています。
大学では、応用栄養学と栄養教諭免許取得のための授業を担当しています。
応用栄養学実習Ⅰ:
幼児向けのアレルギー対応食(卵乳除去食)や、小学生向けの給食献立をグループで考え、実際に調理します。試行錯誤を重ね、何度も献立を修正する過程を通して、献立作成のスキルだけでなく、チームワークやコミュニケーション能力も養います。
栄養教諭関連の授業・ゼミ:
水戸市食育サポーターの活動と連携し、小学校の給食時間に訪問して、子どもたちへの栄養指導を体験します。実際の現場で、対象者の発達段階に合わせた栄養指導やプレゼンテーションのスキルを磨く、実践的な学びを提供しています。


学生・高校生へのメッセージ
朝ドラ「おむすび」のように、「食」は人と人との心を結び、笑顔を広げる力を持っています。そして、私たちの心と体の健康を支える、かけがえのないものです。
常磐大学では、管理栄養士・栄養教諭として、人と地域社会を元気にしたいという熱意あふれる学生を歓迎します。ぜひ、本学のオープンキャンパスにお越しください。また、学生向けに教員採用試験対策の個別相談指導も随時実施しています。
私たちと一緒に、「食」の未来を切り拓きましょう!
常磐大学では、管理栄養士・栄養教諭として、人と地域社会を元気にしたいという熱意あふれる学生を歓迎します。ぜひ、本学のオープンキャンパスにお越しください。また、学生向けに教員採用試験対策の個別相談指導も随時実施しています。
私たちと一緒に、「食」の未来を切り拓きましょう!